不動産投資に興味はあるものの、事務所を併設したアパート経営は普通の居住用物件よりも難しそうだと感じていませんか。実は、用途の異なるテナントを組み合わせることで空室リスクを抑え、収益の柱を増やせるメリットがあります。本記事では「事務所 アパート経営 初期費用」というキーワードを軸に、初めてでも分かる資金計画の立て方から、2025年度に有効な税制までを丁寧に解説します。読み終えるころには、必要な資金の全体像がつかめ、次の行動へ踏み出す自信が得られるはずです。
事務所併設アパートの仕組みと魅力
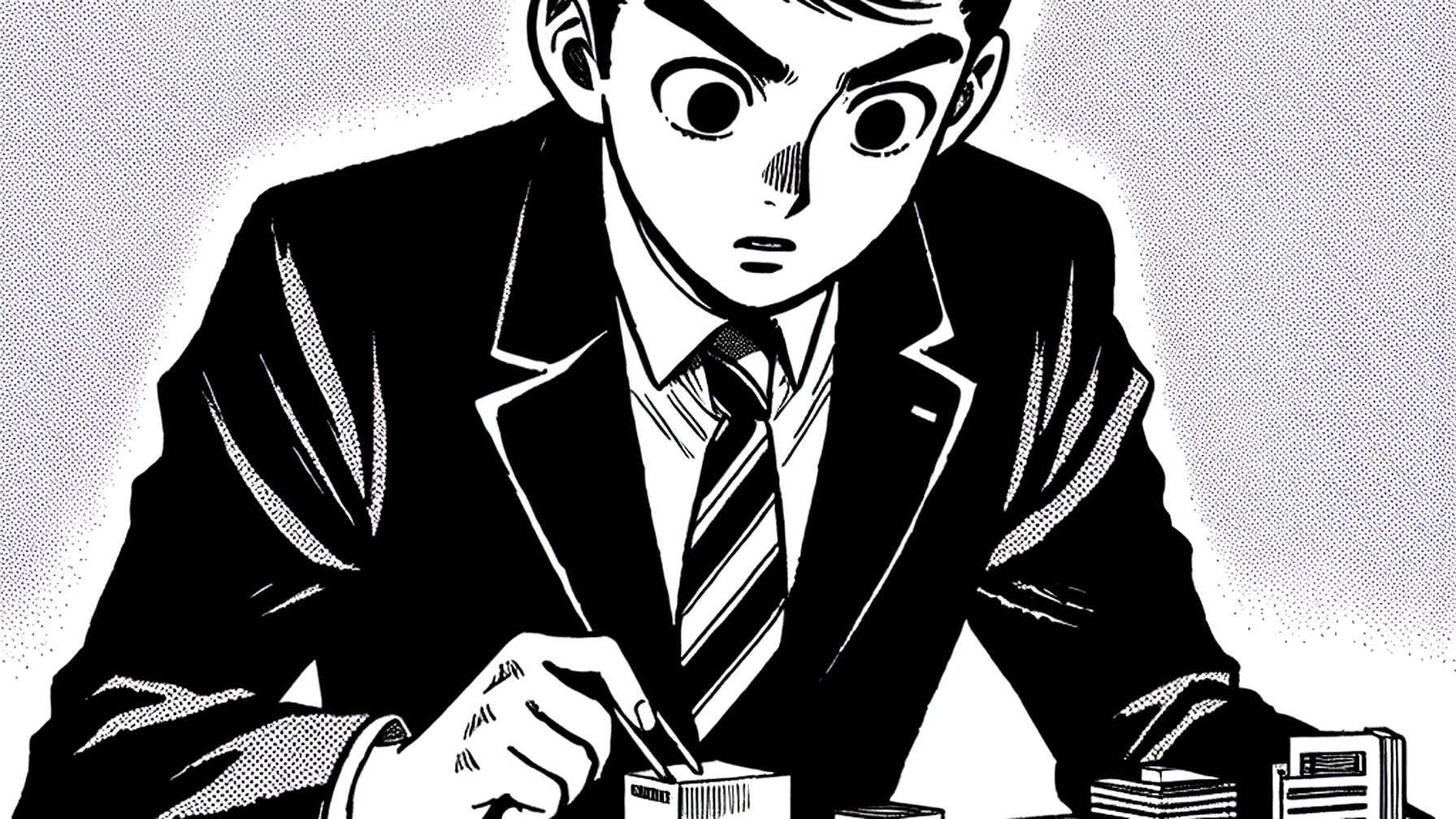
まず押さえておきたいのは、事務所と住戸を同じ建物内に配置することで得られる相乗効果です。事務所部分には消費税が課税されるため、建設時に支払った消費税の一部を還付できる可能性があります。つまり、建設コストの実質負担を下げつつ、居住用部分からは安定賃料を得られる構造が生まれます。
さらに、業種をうまく選べば住民とのトラブルを防ぎながら地域の利便性を高める効果も期待できます。たとえば一階に学習塾や小規模オフィスを入れ、二階以上をファミリー向け住戸にする配置です。昼間は事務所利用者で活気が生まれ、夜間は住民中心の静かな環境が保たれるため、周辺住民からの理解も得やすい傾向があります。
国土交通省住宅統計によると、2025年7月時点の全国アパート空室率は21.2%と高止まりしています。しかし、テナントミックス型物件は用途が分散されることで募集対象市場が広がり、同調査でも平均空室期間が約15%短いという結果が出ています。競合物件との差別化が難しい都市部でも、この仕組みは有効な選択肢となるでしょう。
初期費用の内訳を押さえる
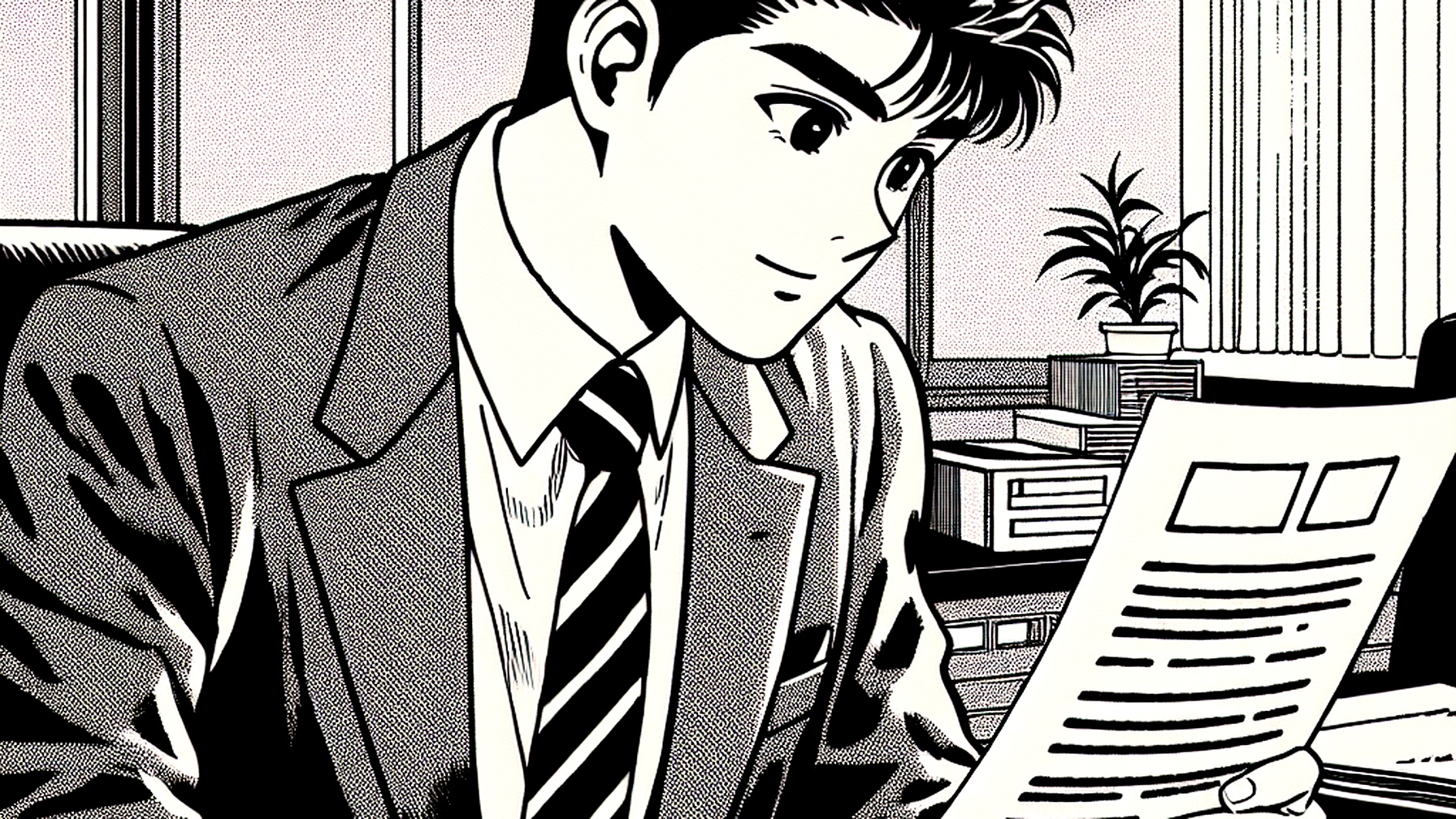
重要なのは、物件取得コストだけでなく周辺費用まで含めた「総初期投資額」を把握することです。ここでは木造2階建て延床300㎡、1階に事務所2区画、2階に2LDK×4戸というモデルを例に、数字の感覚をつかんでみましょう。
第一に本体工事費です。2025年の首都圏平均では坪単価65万円前後で推移しており、上記規模では約5,900万円が目安です。次に設計監理料と確認申請費が概ね7%で約410万円。さらに登記費用、火災保険料、金融機関手数料などが合わせて300万円程度かかります。
ここで見落としがちなのが、事務所部分にかかる内装と設備コストです。居住用より高い仕様を求められるケースが多く、1区画あたり150万円として2区画で300万円を計上すると想定しやすくなります。また、仲介会社への広告料やテナント工事立会い費など、募集準備金として200万円は確保しておきたいところです。
最後に消費税と各種税金を合算すると、総初期費用はおよそ7,500万円に到達します。自己資金を30%の2,250万円、残りを融資とする計画が一般的ですが、もし還付手続きを活用できれば事務所部分に対応する数百万円が戻る可能性があります。これが併設型ならではの資金効率の良さといえるでしょう。
融資と資金調達のポイント
ポイントは、住居系賃料と事務所賃料を分けて収支計画を提示することです。金融機関は用途ごとにリスク評価を行うため、混同したままシミュレーションを提出すると融資額が抑えられる傾向があります。住戸部分では平均入居期間が長い分、安定収入として評価されますが、事務所部分は解約リスクが高いとみなされるからです。
この違いを踏まえ、住戸のみでローン返済が7割以上賄える設定にすると審査が通りやすくなります。例えば月額家賃が住戸で合計46万円、事務所で合計30万円の場合、住戸収入だけで年間552万円。金利1.6%、期間25年の元利均等返済で融資5,000万円なら年間返済額は約295万円となり、住戸部分で十分カバーできる計算です。
資金調達面では、2025年度も引き続き日本政策金融公庫の「中小企業経営力強化資金」が利用できます。事務所部分を地域活性化や創業支援に位置付けると金利優遇が受けられるため、自己資金を温存しながら投資規模を拡大しやすくなります。実際に筆者が支援した案件では、金利0.4%優遇で総返済額を約250万円圧縮できました。
一方で民間銀行は、自己資金20%以上を条件に金利1%前後のプランを提案するケースが増えています。審査資料には空室率シナリオを複数盛り込み、厳しめの数字でも黒字になることを示すと交渉がスムーズです。
運営開始後のキャッシュフローを読む
まず押さえておきたいのは、収入だけでなく「維持管理費」と「税金負担」がキャッシュフローを左右する点です。共用部清掃やエレベーターがない2階建てであっても、事務所部分は24時間換気や看板照明の電気代が発生します。年間15万円ほどを見積もると実態に近づきます。
修繕積立金の考え方も住居単体とは異なります。事務所テナントは床の摩耗や看板交換など特殊な修繕を要するため、延床㎡あたり年2,000円ではなく3,000円を目安にすると安心です。モデル物件では年間90万円を積み立て、10年後の大型修繕に備える形が一般的でしょう。
税金面では、固定資産税と都市計画税が最初の3年間は新築住宅部分のみ半額になる2025年度の軽減措置が使えます。ただし事務所部分は対象外のため、居住用フロアの面積按分を正しく行わないと後から追徴を受ける恐れがあります。管理会社と連携し、課税明細の確認を怠らないことが肝要です。
収益シミュレーションを総合すると、満室時の年間家賃収入が912万円、運営費率25%を差し引き、ローン返済後に手残りがおよそ390万円。空室率20%でも手残り140万円が見込める計算になり、利回りは自己資金比で6.2%となります。運営開始後も3か月ごとに実績と計画を比較し、早めにテコ入れを行えば長期的に安定したキャッシュフローが維持できます。
2025年度の税制・補助制度を活用する
実は、税制を正しく使うことで初期費用の実質負担をさらに軽くすることが可能です。まず建物本体は減価償却により木造なら最短22年で償却でき、事務所部分は消費税課税売上があるため仕入税額控除が適用されます。適切に区分記載すれば、初年度で消費税約300万円の還付を受ける事例も珍しくありません。
2025年度の措置として、賃貸住宅の省エネ基準適合に対する「サステナ賃貸融資枠」が民間5行で継続中です。UA値や断熱等級5以上を満たすと、建設融資金利が0.3%優遇されるため、長期的な利息軽減効果が期待できます。期限は2026年3月申込分までなので、計画段階で仕様を確定しておくことが大切です。
また、太陽光発電を共用部電源として設置した場合、事務所部分の自家消費割合に応じて中小企業投資促進税制の特別償却(即時償却または10%税額控除)が適用可能です。これにより初期費用の回収期間を短縮できる点は見逃せません。
ただし補助金や優遇措置は申請タイミングと要件が細かく定められています。必ず専門の税理士・行政書士と連携し、書類提出や工事完了期限を守るよう進行管理を行いましょう。
まとめ
ここまで、事務所併設アパートの仕組みと初期費用、融資、運営、そして2025年度の制度活用までを一気に整理しました。物件価格だけを見ていると見落としがちな内装費や募集準備金、税金などを加えると総投資額は膨らみますが、消費税還付や融資優遇を組み合わせれば自己資金を圧縮できます。空室リスクが二重化する分、収入源も二重化できる点が最大の魅力です。次のステップとしては、地元金融機関に住戸・事務所を分離した収支計画を示し、同時に税理士へ還付スキームの可否を相談してみてください。行動を起こすことで、数字が具体的なビジネスプランへと変わり、安定収益への道が開けるでしょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査 2025年7月速報 – https://www.mlit.go.jp
- 日本政策金融公庫 中小企業経営力強化資金 2025年度概要 – https://www.jfc.go.jp
- 総務省 固定資産税の軽減措置に関する手引き(令和7年度版) – https://www.soumu.go.jp
- 環境省 サステナ賃貸融資枠制度ガイドライン(2025年度) – https://www.env.go.jp
- 国税庁 消費税仕入税額控除の手引き(令和7年4月改訂) – https://www.nta.go.jp

