円安が続くと、海外旅行や輸入品の値上がりに悩む一方で、「資産はどう守ればいいのか」と不安になる方が増えます。外貨建て資産を直接買うのはハードルが高いものの、国内で円建てのまま国際分散効果を得られる投資先があります。それが不動産投資信託、いわゆるREIT(リート)です。本記事では、円安環境下でも安定したインカムを狙えるJ-REITの仕組みと選び方を解説し、2025年10月時点で有効な制度を踏まえた具体的な活用法を紹介します。読み終わるころには、ご自身に合った「円安時代 REIT おすすめ」ポートフォリオをイメージできるはずです。
円安が家計と投資環境に与えるインパクト
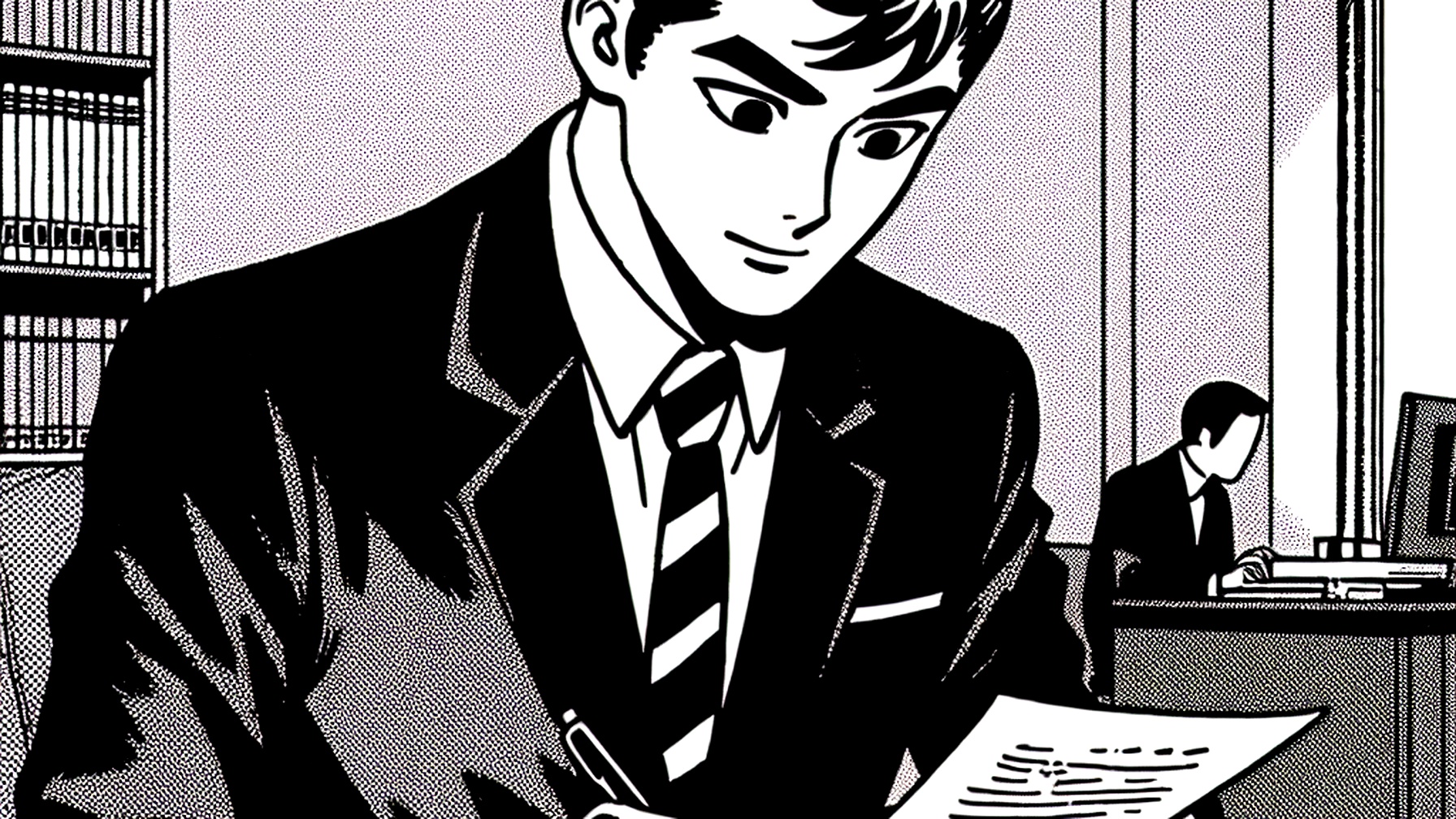
まず押さえておきたいのは、円安が進むと国内外の物価がどう変わるかという点です。日銀の名目実効為替レートを見ると、2021年初頭を100とした場合、2025年9月末は71前後まで低下しています。つまり円の購買力は4年で約3割減りました。輸入コストの上昇が家計を圧迫し、株式市場では輸出企業が恩恵を受ける一方、内需型企業には逆風が吹きます。
一方で、REIT市場への影響はやや複雑です。ホテル型REITは訪日客の増加で稼働率が高まり、分配金の原資が増える傾向にあります。物流施設型は越境ECの拡大で賃料の安定性が高まるため、円安がプラスに働きやすいといえます。また、国内不動産の鑑定評価に海外マネーが流入しやすくなり、物件価格の下支え要因にもなります。
ただし、海外金利の上昇と円安が同時に進むと、外資系投資家が日本のREITを売却し資金を本国へ戻す動きが出ます。この資金フローは価格変動要因になるので、利回りと空室率だけでなく外国人持ち株比率にも目を向ける必要があります。
要するに、円安は生活を圧迫するリスクであると同時に、一部の不動産セクターには追い風をもたらす二面性を持っています。REIT投資では、この点を冷静に見極める姿勢が欠かせません。
REITの仕組みと円安との相性を理解する
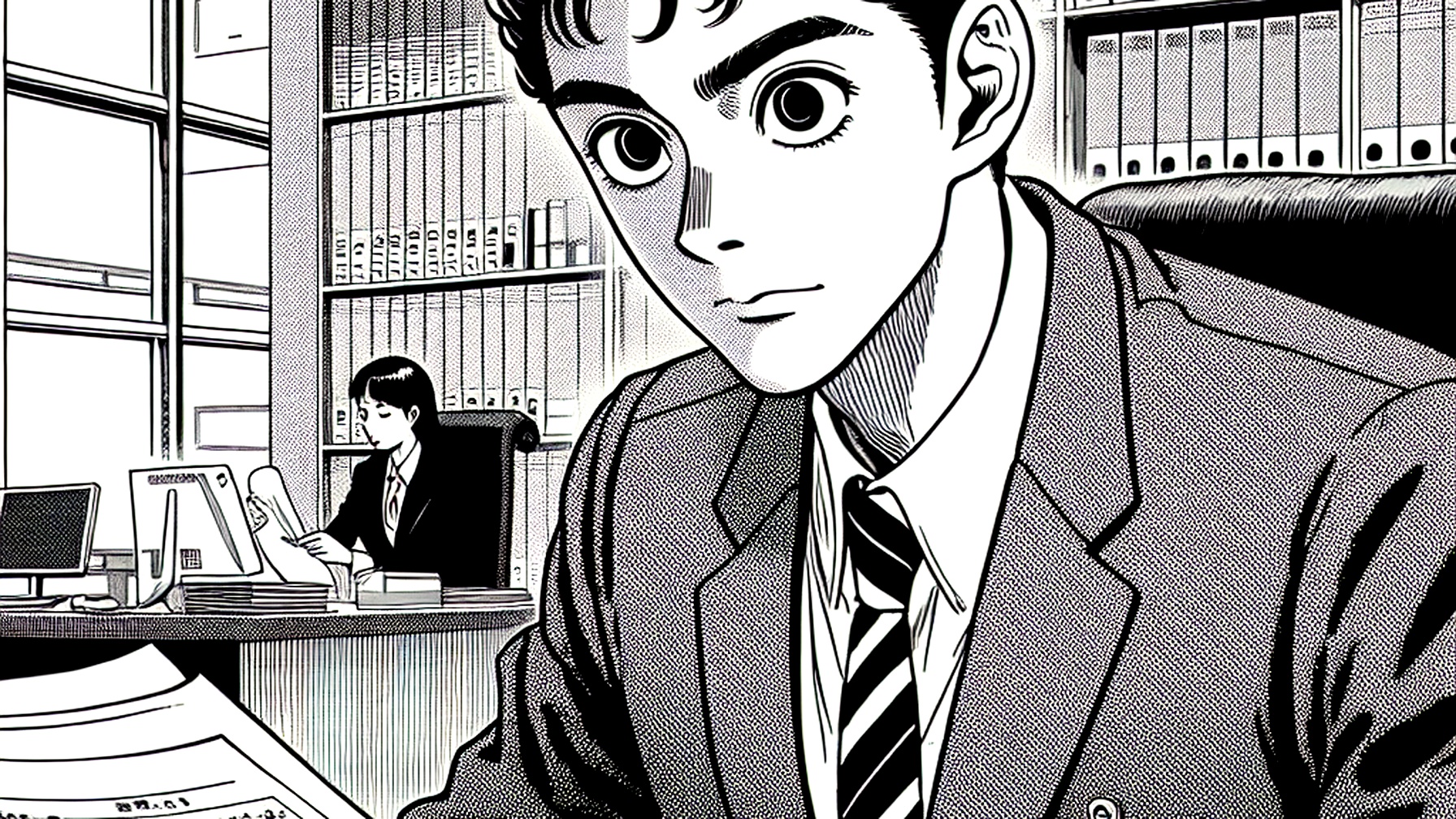
重要なのは、REITが株式と債券の性格を併せ持つハイブリッド資産であることです。投資家は証券取引所を通じて1口数万円から取引でき、REIT運用会社は集めた資金で複数の不動産を保有し、賃料や売却益を分配します。税制上、利益の90%以上を分配すると法人税が免除されるため、分配金利回りが高くなるのが特徴です。
円安局面では、海外収入が円換算で膨らむホテル型・物流型に注目が集まりやすい一方、オフィス型はテナントが国内企業に偏るため相対的に鈍い動きになりがちです。しかし、オフィス型は長期契約が多く賃料のブレが小さいため、円安時に価格が下がれば利回りが上昇する妙味もあります。言い換えると、セクターごとの値動きのズレを利用してポートフォリオを組めば、為替リスクを間接的に分散できるわけです。
2025年10月時点で上場しているJ-REITは63銘柄、総資産は約22兆円です。日銀が保有割合を段階的に縮小しているものの、市場全体の浮動性は高まり売買はしやすくなっています。オープン型不動産ファンドと異なり、日次で価格が分かる点も透明性の高い特徴です。
さらに、REITに投資するETF(上場投資信託)を使えば、1本で複数銘柄に分散しながら売買手数料も低く抑えられます。円安を活かしてインバウンド需要が伸びるホテル型を多めに組み入れたETFと、ディフェンシブなオフィス・住宅型を均等に組むETFを組み合わせれば、相場の偏りをコントロールしやすくなります。
ポイントは銘柄選びと分配金利回りの持続性
まず押さえておきたいのは、REIT選定で最も重視すべき指標が「NAV倍率」と「FFO利回り」であることです。NAV倍率は基準価額が保有不動産の時価総額に対して割安かを示し、1倍を下回れば理論的に買い場とされます。一方、FFO(運用による資金)利回りは賃料キャッシュフローから修繕費などを差し引いた実力値で、分配金の持続性を見るのに役立ちます。
たとえば、2025年9月末時点でNAV倍率が0.9倍前後のオフィス特化型REITは、円安でオフィス需要に不透明感が漂う中でも安値拾いのチャンスといえます。また、FFO利回りが5%を超える物流型REITは、越境ECの好調さが背景にあり、インフレ局面で賃料改定が期待できるため注目度が高いです。
加えて、LTV(総資産に対する借入金比率)が50%を超える銘柄は、海外金利上昇局面で調達コストが上がるリスクがあります。資金繰り表を定点観測し、返済期限が短期に集中していないか確認することが欠かせません。つまり、表面利回りが高くても負債が重く調達金利が変動性の場合は、一転してリスク資産になり得るわけです。
個別銘柄を絞り込むステップとして、上場REIT協会が毎月公開するデータや、金融庁EDINETで開示される有価証券報告書を読み込むと、物件所在地やテナント属性まで把握できます。これらの情報を基に、円安メリットが大きいセクターを厚めに配分し、景気連動性が低い住宅型を保険として組み入れると、バランスの取れたポートフォリオが完成します。
2025年度の税制と制度を味方に付ける
実は、2024年に刷新された新しいNISA制度は2025年度も継続し、年間投資枠360万円のうち成長投資枠でJ-REITやREIT ETFを購入すれば、分配金と売却益が無期限で非課税です。口座開設条件は従来と同じですが、クレジットカード積立と組み合わせるとポイント還元も狙えます。
また、個人型確定拠出年金(iDeCo)では、2025年度もREITインデックスファンドを選択可能です。拠出時に所得控除を受けられ、運用益も非課税、受取時には退職所得控除や公的年金等控除が適用されるため、実質的な節税効果はNISA以上になる場合があります。
法人として不動産管理会社を設立する場合、2025年度税制改正大綱ではREIT分配金への益金不算入割合に変更はなく、配当控除も引き続き適用されます。ただし、REIT ETFを売買する際の証券税率は約20%のままで、節税を狙うならNISA口座との併用が現実的です。
そのほか、2025年度の小規模企業共済等掛金控除を活用し、現金比率を高めながらREITの値動きに備える手もあります。要するに、非課税口座と所得控除を組み合わせることで、円安メリットを最大化しつつ税負担を抑える仕組みが整備されているのです。
円安時代におすすめしたい具体的ポートフォリオ
ポイントは、円安メリットが大きいセクターと守りのセクターを7対3程度で組み合わせることです。たとえば、ホテル・物流・データセンター型の3銘柄を合計70%、住宅・ヘルスケア型を30%とし、月次でリバランスする方法が考えられます。この比率なら、訪日客数が伸び悩んだ場合も住宅賃料の安定収益で下支えできます。
具体例として、ホテル特化型Aリートは2025年6月決算で分配金利回り5.8%、インバウンド比率が65%に達し円安恩恵が直撃します。物流特化型Bリートは越境EC企業との20年契約を複数持ち、稼働率99%超をキープしています。データセンター型Cリートは、クラウド需要に連動して長期固定賃料契約を採用し、FFO利回りは4.9%です。
一方、住宅型Dリートは首都圏ワンルームを中心に分散し、LTV40%台と財務健全性が高いことから守りの役割を担います。ヘルスケア型Eリートは高齢者施設を保有し、医療法人との長期契約で安定収益を確保しています。円安の影響を受けにくい分、相場全体の調整局面で価格が下がりにくいのが魅力です。
最後に、投資額配分の目安として、月間積立ならホテル・物流・データセンター型ETFを2万円ずつ、住宅・ヘルスケア型ETFを1万円ずつ購入し、NISA枠内に収めます。四半期ごとに評価額をチェックし、想定比率から±5%ずれたら売買してリバランスするだけで、過度な売買手数料を避けつつシンプルに運用できます。こうした仕組み化が、円安による市場変動に振り回されないための鍵となります。
まとめ
円安が長期化すると、現預金だけでは購買力が目減りしやすくなります。その対策として、国内で円建てのまま分散効果を享受できるJ-REITは魅力的な選択肢です。円安メリットが大きいホテル・物流型を軸に、住宅・ヘルスケア型で守りを固め、NAV倍率やFFO利回りをチェックしながら銘柄を選べば、安定したインカムと値上がり益の両方を狙えます。さらに、新NISAやiDeCoを活用すれば分配金が非課税になり、複利効果を加速できます。ぜひ本記事で得た視点を生かし、ご自身の資産形成プランに「円安時代 REIT おすすめ」ポートフォリオを組み込んでみてください。
参考文献・出典
- 日本銀行「為替レート統計」 – https://www.boj.or.jp/statistics/market/forex/fxdaily/index.htm
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp
- 一般社団法人 投資信託協会「REIT市場データ」 – https://www.toushin.or.jp
- 金融庁 EDINET – https://disclosure.edinet-fsa.go.jp
- 内閣府 観光庁「訪日外国人統計」 – https://www.mlit.go.jp/kankocho

