不動産投資には興味があるものの、物件を直接買うのはハードルが高いと感じる方は多いでしょう。そんなとき少額から投資できるREIT(不動産投資信託)が候補に上がりますが、配当への税金や実際の口コミが分かりにくく、一歩踏み出せないという声も耳にします。本記事では2025年10月時点の最新制度を踏まえ、REITの税金構造を丁寧に解説し、投資経験者の口コミも交えてメリットと注意点を整理します。読み終えるころには、仕組みを理解したうえで自分に適した投資判断ができるようになるはずです。
REITの基本と魅力を押さえる
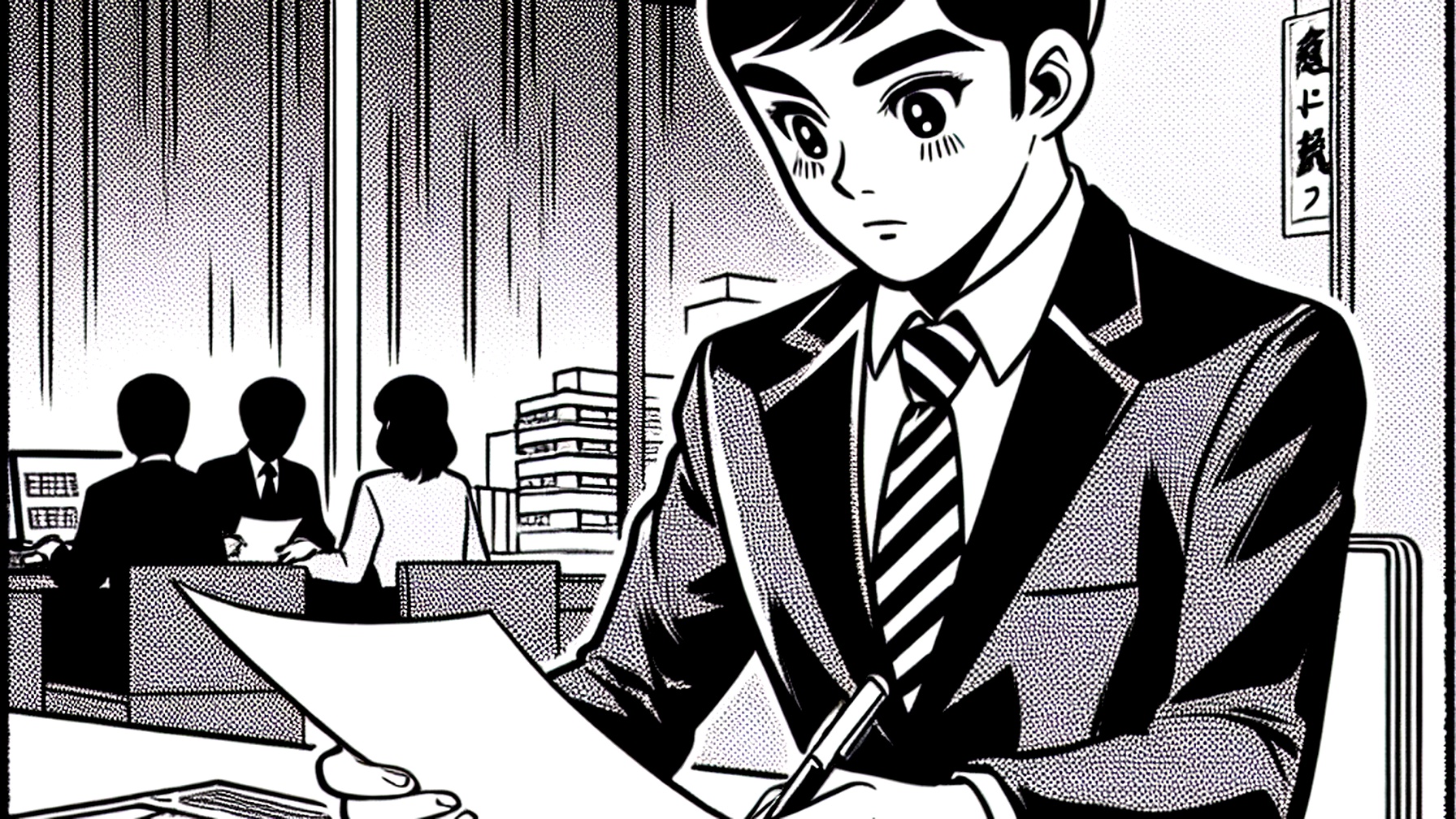
まず押さえておきたいのは、REITが上場株式と同じように証券取引所で売買される投資信託だという点です。投資家は住宅やオフィスビルを一棟まるごと買うのではなく、複数物件に分散投資するファンドの受益権を取得します。つまり、一口数万円からプロ並みの不動産ポートフォリオに参加できるわけです。
また、投資法人が得た賃料や物件売却益の90%以上を配当に回すと法人税が実質的に免除される「みなし配当課税」の仕組みも魅力です。これにより、一般的な国内株よりも高い分配利回りが期待できます。金融庁の2025年度末データによると、東証REIT指数の平均分配利回りは3.9%前後で推移しており、定期預金の数十倍です。
一方で、価格変動は株式市場の影響を受けやすく、不動産市況が悪化した場合の下落リスクも看過できません。加えて、投資法人の運用手数料や物件修繕費が分配金を圧迫するケースもあるため、目論見書の詳細を確認する姿勢が欠かせます。
つまり、REITは「少額・分散・高利回り」という長所があるものの、株式投資に近い値動きや実物不動産特有のリスクも併せ持つ金融商品です。次のセクションでは、その配当にかかる税金を整理し、ネット証券でよく見かける「税引後利回り」の計算方法を詳しく見ていきます。
2025年度のREIT税金と控除の仕組み
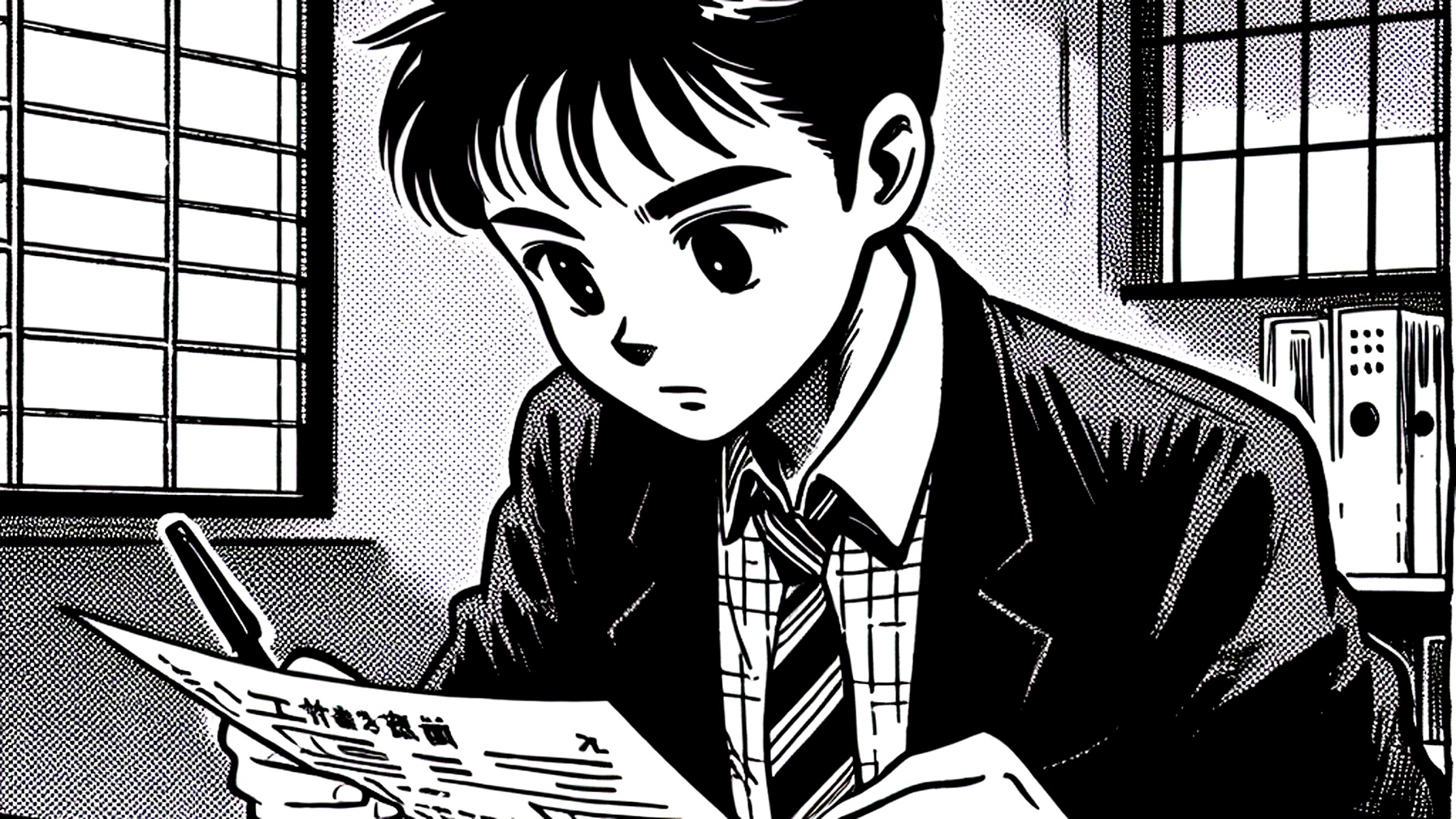
重要なのは、REITの配当(正式には「投資口分配金」)に課される税率が上場株式の配当と同じ20.315%である点です。内訳は所得税15.315%と住民税5%で、いずれも源泉徴収されます。そのため、証券口座に振り込まれる金額は自動的に税引後となります。
確定申告で申告分離課税を選択すれば、譲渡損失と配当の損益通算が可能です。たとえば保有REITの値下がりで50万円の譲渡損が出た場合、同年にもらった分配金の税額を相殺できます。国税庁の資料によると、この仕組みにより平均5.5%程度の節税効果が得られたケースも報告されています。
さらに、2024年に制度拡充された「成長投資枠つきNISA」は2025年も継続しており、年間240万円までの投資が非課税で運用可能です。REITもこの枠に含まれるため、分配金と売却益のどちらにも税金がかかりません。非課税枠は最長5年間なので、長期保有前提の投資家にとって大きなメリットとなります。
一方で、一般口座や特定口座でREITを保有していても、生命保険料控除などの所得控除と直接相殺できるわけではありません。また、海外REITの場合は現地課税が発生し、外国税額控除を利用する手続きを要する点に注意しましょう。思わぬ二重課税を避けるため、購入前に運用報告書に記載された源泉地国税率を確認することが大切です。
口コミに見るメリットとリスクのリアル
実は公式資料だけでは見えてこない点を把握するうえで、既存投資家の口コミは貴重なヒントになります。大手ネット証券の掲示板やSNSでは「分配金が安定していて助かる」という声の一方、「金利上昇局面で分配金が減るのでは」といった不安も散見されます。
例えば、日本銀行が2024年末に実施したマイナス金利解除後、あるオフィス系REITの価格は1か月で8%下落しました。こうした値動きは口コミでも大きく取り上げられ、「配当利回りが上がって見えるが、実際は物件取得コストが重いから慎重に」という意見が共有されています。つまり、市場金利の上昇は物件取得時の借入金利を押し上げ、将来の利益を圧迫する可能性があるのです。
一方で、物流施設特化型REITに関しては「EC需要の追い風で空室率が低く、配当も右肩上がり」という肯定的な口コミが多数を占めます。国土交通省の物流統計によると、2025年時点の大型物流施設の平均空室率は2.1%と低水準を維持しており、データが口コミを裏づける形です。
ただし、口コミはあくまで個人の感想であり、投資判断の最終責任は自分にあります。特定の銘柄に過度にポジティブまたはネガティブな意見が集中しているときほど、運用報告書や決算資料に立ち返り、数字で裏づけを取る姿勢が不可欠です。
税負担を抑えるための実践的アプローチ
ポイントは、税金を「コスト」と捉え、投資戦略と組み合わせて最適化することです。まずNISAをフル活用し、非課税枠で高配当の国内REITを買い付けると、分配金がそのまま手取りになります。配当利回り4%の銘柄に100万円投資した場合、年間4万円の分配金が非課税になる計算です。
次に、特定口座で保有しているREITが値下がりした場合は、年末に損出しを行うことで株式や他REITの配当と損益通算できます。損出しとは評価損を確定させて翌日に買い戻す手法で、国税庁も合法的な節税策として認めています。ただし手数料と価格変動リスクがあるため、流動性の高い銘柄で行うのが無難です。
加えて、法人を設立してREITを保有する方法もあります。法人税率は利益800万円以下で15%台に抑えられるため、高額所得者が個人で20.315%の税率を負担するより有利になることがあります。ただし法人設立には登記費用や会計コストがかかり、節税メリットが固定費を上回るか検証が必須です。
最後に、「配当再投資」を行うと複利効果が得られるだけでなく、分配金課税を繰り延べる効果も期待できます。具体的には、源泉徴収後の分配金で追加口数を買い増し、受取額を少額に抑えつつ保有資産を増やします。東京証券取引所の試算では、配当再投資を20年間続けた場合のリターンは、単純受取より平均1.4倍に達しました。
まとめ
本記事ではREITの概要、2025年度の税制、口コミから読み取れる実感、そして具体的な節税策を解説しました。REITは少額から高利回りを狙える一方、相場変動や物件の質によるリスクがあるため、制度と口コミの両面から情報を吟味する姿勢が大切です。NISAの非課税枠や損益通算を駆使すれば税負担を軽減でき、配当再投資で複利を効かせれば長期的な資産形成も可能です。まずは少額で試し、分配金・値動き・税コストを体感しながら、自分に合った投資スタイルを育てていきましょう。結論として、知識と仕組みを味方につければ、REITは初心者でも取り組みやすい不動産投資の入り口となります。
参考文献・出典
- 金融庁「金融商品取引業等に関する統計」2025年3月 – https://www.fsa.go.jp
- 東京証券取引所「東証REIT指数・統計情報」2025年9月 – https://www.jpx.co.jp
- 国税庁「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収」令和7年度版 – https://www.nta.go.jp
- 国土交通省「不動産市場動向レポート」2025年7月 – https://www.mlit.go.jp
- 日本銀行「金融政策決定会合議事要旨」2025年6月 – https://www.boj.or.jp

