都市部の不動産価格が高騰し、個人で一棟を購入するハードルが上がったいま、少額から参画できる不動産クラウドファンディングに注目が集まっています。しかし「想定利回りは本当に達成されるのか」「木造物件は耐久性が心配ではないか」といった疑問を抱く人も多いでしょう。本記事では、2025年10月時点の最新データをもとに、木造案件の利回り水準とリスク、そして案件選びの着眼点まで丁寧に解説します。最後まで読めば、自分に合った投資判断を下すための具体的なヒントが得られるはずです。
木造案件がクラウドファンディングで増えている理由
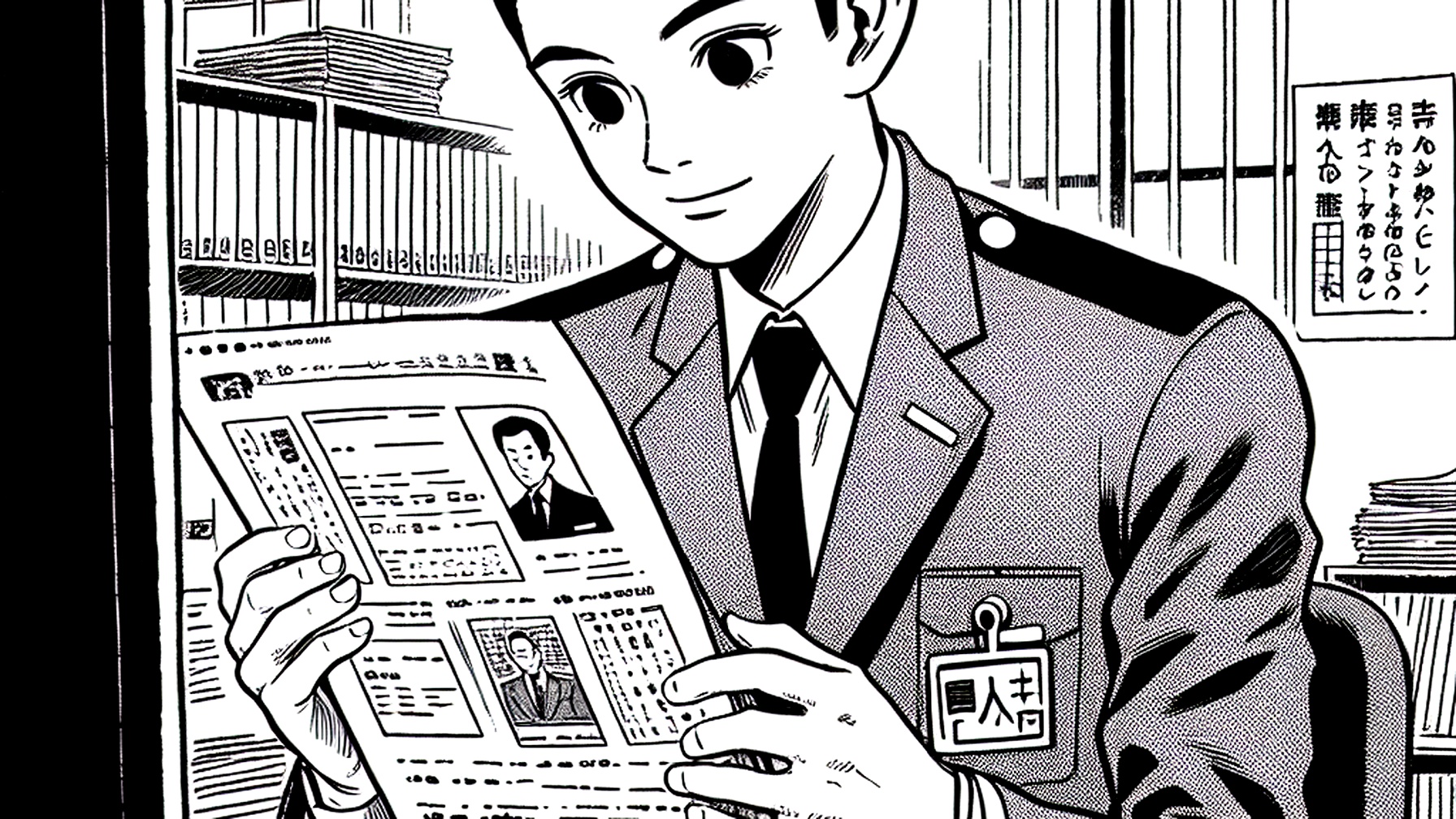
まず押さえておきたいのは、木造物件がオンライン型ファンドで増加している背景です。建設コストの上昇が続くなか、鉄筋コンクリート造(RC造)より安価に建てられる木造は、開発会社にとっても魅力的な選択肢になっています。また、建築基準法の改正で耐震性能が底上げされ、木造でも資産価値を維持しやすくなったことが追い風です。
さらに、環境への配慮も見逃せません。国土交通省は2024年度から「木造建築促進策」を進めており、二酸化炭素吸収源としての木材利用を推奨しています。ファンド運営会社がこの流れに乗り、ESG投資の観点から木造案件をラインナップするケースが増えました。つまり、市場全体で木造需要が高まりつつあるため、クラウドファンディングでも選択肢が広がっているのです。
一方で、木造は法定耐用年数が22年とRC造の47年より短く、長期保有を前提とする場合はリスク管理が欠かせません。だからこそ、運用期間が2〜5年程度に設定されるクラウドファンディングと相性が良いとも言えます。短期運用なら耐用年数の影響を受けにくく、出口戦略を描きやすいからです。
現在の利回り水準と市場動向
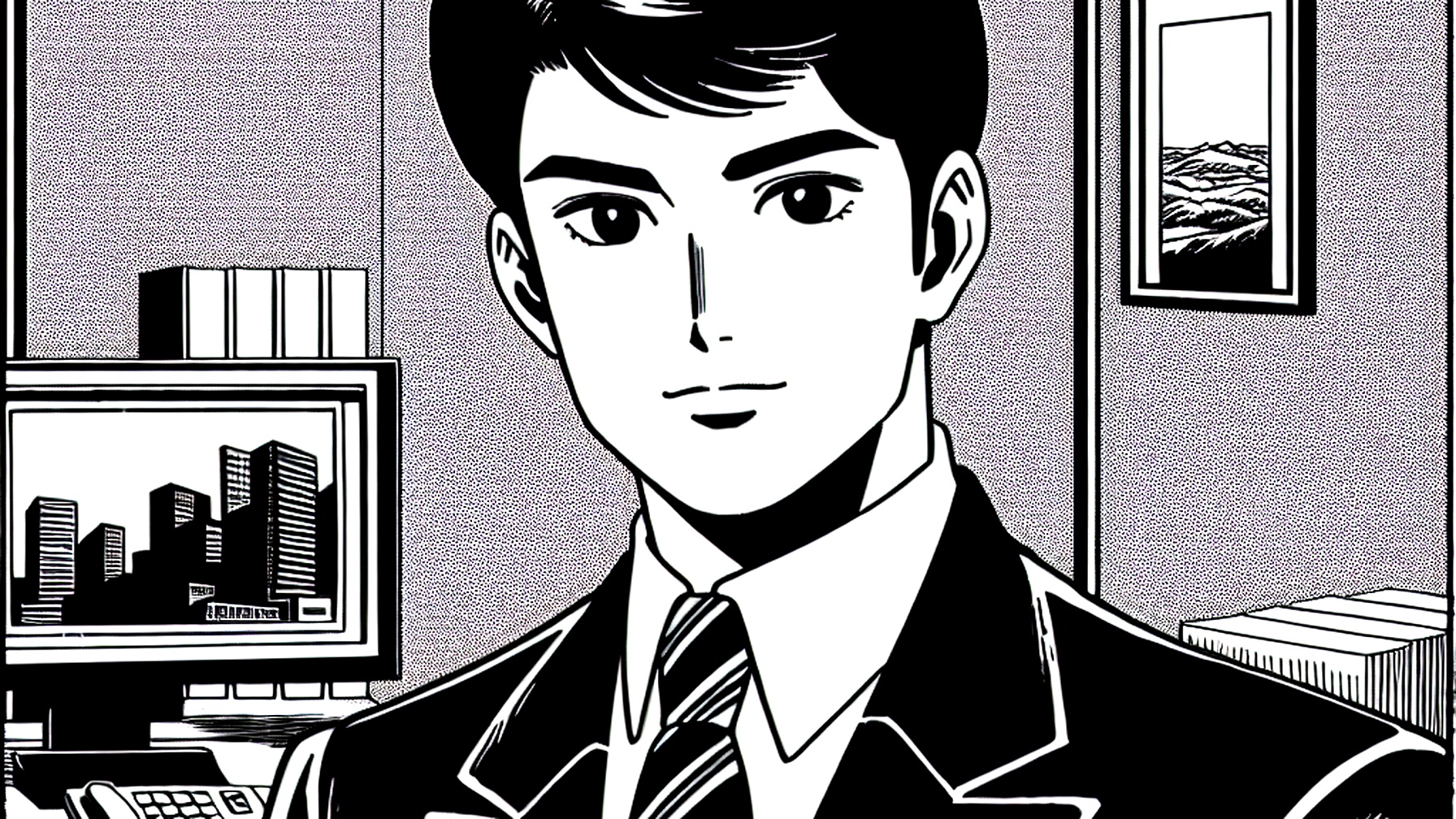
重要なのは、実際の利回りがどの程度で推移しているかを把握することです。日本不動産研究所の2025年7月調査によると、東京23区の木造アパート一棟投資の表面利回りは平均5.1%でした。これに対し、同時期のクラウドファンディング木造案件の想定利回りは6〜8%が中心帯となっています。
なぜ高めに設定されるかといえば、短期運用による売却益を加味しているためです。例えば、築浅木造アパートを用地取得から3年で売却するモデルでは、家賃収入に加え、開発益が上乗せされます。ただし、想定はあくまでも想定であり、家賃下落や売却価格の伸び悩みがあれば実利回りは低下します。
また、融資環境も利回りに影響します。2025年10月時点で日本銀行は政策金利を0.1%に据え置いており、金融機関のアパートローン金利は変動型で年1.8〜2.3%が一般的です。クラウドファンディング案件では運営会社が一括借入を行い、そのコストを上回るリターンを投資家へ配分します。金利が大幅に上昇すれば、運営コストが膨らみ利回りが圧迫されるため、将来的な金利動向にも注意が必要です。
つまり、現在の利回りは魅力的に見えても、金利リスクと物件価格の変動リスクを織り込んで判断することが欠かせません。想定利回りだけを追い求めるのではなく、その数字がどのような前提で算出されているのかを確認しましょう。
木造物件特有のリスクと対策
ポイントは、木造ならではのリスクを正しく理解し、対策が取られているかを見極めることです。第一に挙げられるのが、修繕費の発生時期です。木造は外壁や屋根の塗装メンテナンスを10年前後で行うのが一般的で、RC造より修繕サイクルが短くなります。ファンド期間内に大規模修繕が予定されていないか、運営計画を必ずチェックしましょう。
次に耐火性能です。2019年の建築基準改正により防火・準防火地域でも3階建て木造が認められるようになりましたが、耐火仕様のコストがかさむ点はデメリットになり得ます。ファンド資料で使用材料や建築確認済証の有無を確認し、コストとリターンのバランスを把握しておくと安心です。
そして空室リスクも見逃せません。総務省「住宅・土地統計調査」(2024年版)によれば、東京都のワンルーム空室率は12.1%で上昇傾向にあります。木造アパートの多くはワンルームタイプであるため、立地が駅徒歩10分以内か、近隣に大学や企業があるかなど、賃貸需要を支える要因があるかを確認してください。
最後に天災リスクです。木造は地震で全壊するイメージを持たれがちですが、現在は耐震等級2以上を取得する案件が増えています。ファンドの募集ページに耐震等級を明記している場合は必ず確認し、明記がない場合は質問窓口で聞いてみると良いでしょう。
案件選びで確認すべきポイント
実は、利回りだけでなく運営会社の実績や情報開示姿勢が投資成績を左右します。まず運営会社の累計募集額と償還実績を確認しましょう。過去に元本欠損があれば、その要因と再発防止策を探ることが重要です。また、ファンドごとに優先劣後出資割合が設定されているかどうかも要チェックです。劣後出資が高いほど、投資家にとって安全余裕が大きいといえます。
次に運用期間と出口戦略です。木造案件は3年以内に売却して開発益を狙うものが多い一方、5年以上の長期運用型も存在します。自分の資金計画に合わせて、途中解約ができないリスクを許容できるかを考える必要があります。
さらに、収益シミュレーションがどの程度の空室率や金利上昇を織り込んでいるかも確認しましょう。楽観シナリオだけではなく、空室率20%、金利上昇1.5%といった厳しめの前提も提示している会社は信頼度が高い傾向にあります。
案件によっては地方都市の再開発プロジェクトを組み込むケースもあります。国土交通省が2025年度に継続している「コンパクト・シティ形成支援事業」の対象地区なら、自治体の補助を受けてインフラ整備が進むため、出口価格の上振れを狙える可能性があります。ただし、補助金の採択結果が確定しているかどうかは必ず確認してください。
2025年度の税制優遇と資金計画の立て方
まず押さえておきたいのは、クラウドファンディングから得た分配金が雑所得として総合課税される点です。所得税率が高い人は、他の控除と組み合わせて税負担を軽減する戦略が求められます。2025年度も継続している「小規模企業共済等掛金控除」を利用すれば、個人事業主やフリーランスが節税しつつ投資資金を確保できます。
一方、法人で投資する場合は、建物の割合を多く計上して減価償却費を活用する手法が一般的です。木造なら4年で一括償却できる「少額減価償却資産の特例」(取得価額が30万円未満)が使いやすく、中小企業のキャッシュフロー改善に役立ちます。ただし、同特例は1年度あたり300万円までの上限があるため、複数案件に分散投資する際は購入額に注意しましょう。
資金計画を立てる際は、運用期間中に再投資する余裕資金を残しておくことも大切です。例えば、300万円を3年間6%で運用した場合、税引後の手取りは約40万円前後になります。これを元本に上乗せして次の案件に投資すれば、複利効果を得ながらリスク分散が図れます。
最後に留意したいのが、2025年度の「NISA」制度拡充です。クラウドファンディングは現状NISA対象外ですが、同じポートフォリオ内で株式やREITを非課税枠で保有すれば、全体の税負担を抑えつつリスクを散らすことが可能です。つまり、ファンド投資と他の資産運用を組み合わせる視点が、今後さらに重要になっていくでしょう。
まとめ
木造不動産クラウドファンディングは、少額から参加できる手軽さと6〜8%前後の想定利回りが魅力ですが、修繕費や空室率、金利上昇といったリスクを正しく見積もることが欠かせません。運営会社の実績、優先劣後構造、出口戦略の妥当性を丁寧に確認すれば、木造の短い耐用年数を逆手に取った短期運用でキャッシュを回すことも十分に可能です。まずは気になる案件の情報開示資料を読み込み、自分の資金計画とリスク許容度に合うかを判断してみてください。適切な知識と準備があれば、現在の市場環境でも堅実なリターンを狙えるはずです。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp
- 国土交通省 木造建築促進策資料 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 住宅・土地統計調査 2024年 – https://www.stat.go.jp
- 日本銀行 金融政策決定会合資料 2025年9月 – https://www.boj.or.jp
- 国税庁 タックスアンサー 雑所得の課税 2025年版 – https://www.nta.go.jp

